はじめに
「民間学童って、どうしてあるんだろう?」
川崎市では「わくわくプラザ」という公的な放課後預かりサービスがあり、基本的に誰でも無料で利用できます。
にもかかわらず、月謝がかかり、保護者の関わりも求められる民間や自主運営の学童保育をあえて選ぶ家庭もあります。
私自身も最初は「どうして?」と疑問に思っていました。
そしてもう一つ、心に引っかかっていたのは『なぜわざわざ作ったんだろう?』という疑問でした。
なぜ学童指導員、保護者たちが話し合い、時間や労力をかけて、自分たちで運営する学童を立ち上げようと思ったのか?
それは、「ただ預かる」だけでは足りないと感じた人たちが、子どもたちの放課後に“育ち”の場を残したいという思いを持っていたから。
この記事では、公的サービスとの違いを踏まえながら、民間・自主運営の学童が何を大切にしているのか、そしてなぜ今も地域に必要とされているのかをお伝えします。
■ わくわくプラザとは?公的サービスの特徴と限界
・誰でも利用できる安心の制度
川崎市が運営する「わくわくプラザ」は、小学校の敷地内などを活用して提供される、全児童対象の放課後居場所事業です。
希望すれば誰でも登録・利用でき、基本的には無料(一部保険料や教材費あり)という手軽さと安心感があります。
共働き世帯に限らず、すべての家庭に“放課後の居場所”を開くという理念は、多くの家庭の支えとなっています。
・自由遊び中心、教育的関与は少なめ
わくわくプラザでは、子どもたちが自由に遊べることが基本方針です。
学習支援や活動プログラムは原則として行われず、あくまで「見守り」を重視した運営がなされています。
そのため、宿題のサポートやコミュニケーションを通じた教育的関わりはほとんど期待できない点もあります。
・一人ひとりに合わせた関わりは難しい
支援員の配置や子どもとの関わり方も、民間学童に比べて画一的になりやすいという声があります。
人数も多く、異年齢の関わりや個々の個性に寄り添う支援が難しいため、「集団の中の一人」として過ごす印象を受けることも。
子どもの性格や家庭の価値観によっては、「物足りなさ」や「合わなさ」を感じることもあります。
■ 民間・自主運営学童の理念とは
・「ただ預かる」ではなく「育てる放課後」
民間学童や自主運営の学童が目指しているのは、単なる“預かり”ではなく、子どもにとっての育ちの場です。
放課後の時間を「空白の時間」としてではなく、「学び」「人との関わり」「自己表現」の機会として捉え、子どもの成長にとって価値ある時間にしようという理念があります。
家庭や学校ではできない経験を、安心できる環境の中で積み重ねることを大切にしています。
・非認知能力(やり抜く力・共感・自己肯定感)を育てる
勉強の点数など“数値化”できる力ではなく、「自分で考え、行動し、仲間と協力する」ような、非認知能力を育てることが重視されています。
例えば──
・おやつ当番や掃除当番をやりきる中で「やり抜く力」
・トラブルも含めて話し合う中で「共感力」
・異年齢の中で役割を持つことで「自己肯定感」
このような“人としての土台”は、社会に出てからも大切な力であり、学童での経験がその基礎になります。
・異年齢での関わり、子ども主体の話し合い
民間・自主運営学童では、1年生から6年生までが混ざって過ごす縦割り活動が基本です。
年上の子が年下の子を自然に助けたり、年下の子が頼ることで信頼関係を築いたりと、学校とは違う形の人間関係を学ぶことができます。
また、「帰りの会」や「班会議」などで子どもたち自身が話し合い、活動の方向性を決めていくスタイルも特徴です。
『自分の意見が認められる場』として、自己表現の大切さや他者との違いも自然に学んでいきます。
・信頼できる大人の存在が育ちの土台に
もう一つ、民間・自主運営学童の大きな魅力が、支援員(指導員)との距離の近さです。
子どもと丁寧に関わり、一人ひとりの気持ちや状態を日々見守ってくれる大人の存在は、家庭でも学校でもない“第3の安心できる場所”をつくり出します。
特に不安定になりがちな低学年の時期に、「わかってくれる大人がいる」「安心して甘えられる場所がある」という経験は、子どもの心の安定と自己肯定感の土台になります。
■ なぜ支援員、保護者たちは自主運営の学童を作ったのか?
・川崎市の制度転換(わくわく導入)と公的学童の廃止
2002年、川崎市では、すべての小学生に放課後の居場所を提供することを目的に、「わくわくプラザ事業」がスタートしました。
これに伴い、それまで各地で運営されていた『公設の学童保育(登録制・定員制の支援型学童)』は廃止されました。
制度としては公平性が高まりましたが、その一方で、一人ひとりの子どもへの丁寧な支援や成長に関わる保育の質が後退したという声も少なくありません。
・「本当にこのままでいいのか?」という現場からの声
制度変更に対して、最も早く違和感を覚えたのは、子どもたちと日々向き合っていた学童の指導員たちでした。
「この子たちの成長を、もっと支えていきたい」「ただ遊びを見守るだけでなく、育ちに関わる学童を残したい」そんな思いが、現場から生まれました。
やがてその想いは、保護者たちにも共感の輪を広げ、「地域に根ざした学童保育を、自分たちでつくる」という自主運営型学童の立ち上げにつながっていきました。
・“預ける”ではなく“見守る・育てる”場を地域に残したかった
民間の自主運営学童は、単なる“預かり”ではなく、『子どもを支える“もう一つの育ちの場”』を目指して生まれました。
指導員と保護者が協力し、子どもたちの個性に寄り添いながら、安心して過ごせる放課後を一緒につくり上げていく。
それは、“家庭でも学校でもない場所”で、子どもたちの心を支える、貴重な存在になっていきました。
・運営は大変でも、「子どもの育ち」に関われる意義
もちろん、保護者が運営にも関わる自主学童には、大変さもあります。
それでも、子どもたちの関わり合いや成長を間近で見守り、自分の手でその環境を整えることができる経験は、親としてもかけがえのない学びになります。
指導員の想いと、保護者の願いが重なり合いながら、子どもたちが育ち合う空間が少しずつ形になっていった。それが、今の自主運営学童につながっています。
■ 実際に通ってわかった、自主運営ならではの価値
・「ただ預ける」のではなく「自分らしく過ごせる」
自主運営の学童に通う中で感じたのは、子どもが「誰かに合わせて頑張る」のではなく、自分のままでいられる安心感があるということでした。
学年や性格に関係なく、その子らしさを大切にしながら見守ってくれる大人たちの存在が、子どもの心を柔らかく包んでくれます。
ときには甘えて、ときには反発して、それでも毎日「ここにいたい」と思える場所──
それが、単なる“預かり”ではない、育ちの居場所であることを実感しました。
・学童での生活が、家庭や学校とは違う育ちを与えてくれる
家では親子、学校では先生と生徒という関係の中で育つ子どもたち。
でも学童では、子ども同士の関わりが中心となり、「対等な仲間」として過ごす時間が長くなります。
遊びや話し合いの中で起きるちょっとしたトラブルや感情のぶつかり合いも、成長のきっかけになります。
異年齢の子と関わることで、助け合うこともあれば頼ることもあり、人との関係性を自分なりに築いていく力が育っていくのを感じました。
・親も共に育ち合う、“地域ぐるみ”の子育ての実感
自主運営の学童では、保護者同士が顔を合わせ、協力し合う機会も多くなります。
「お互いさま」の気持ちで子どもを送り迎えしたり、行事の準備を一緒にしたりと、自然と地域の中に関係性が生まれるのです。
最初は「大変そう…」と思っていた運営への関わりも、実際には子どもの姿を間近で見ることができる、親にとっての貴重な育ちの時間でした。
子どもとだけでなく、親同士・地域とつながりながら子育てができる──
そんな実感を持てることこそ、自主運営学童の最大の魅力かもしれません。
■ まとめ|育ちの放課後という選択肢
民間学童や自主運営の学童には、確かに大変な面もあります。
保護者の関わり、運営の工夫、行事の準備…手間も時間もかかります。
それでも私たちがそこに価値を見いだすのは、ただ預けるだけではない“育ちの放課後”があるからです。
子どもが自分らしくいられる場所、
誰かに見守られながら、仲間とともに育ち合う時間。
そして、親としても学びながら関われる、地域ぐるみの子育て。
わくわくプラザのような公的サービスも素晴らしい選択肢です。
でも、もし「もっと深く子どもに関わる学童があったらいいな」と思ったなら──
こうした民間・自主運営の学童があることも、ぜひ知っておいてほしいと思います。
どちらが正しいというよりも、「うちの子に合っているかどうか」
家庭にとっていちばん安心できる居場所を、ゆっくり、じっくり選んでくださいね。
そしてその中に、こうした地域の学童も選択肢として届いてくれたら嬉しいです。
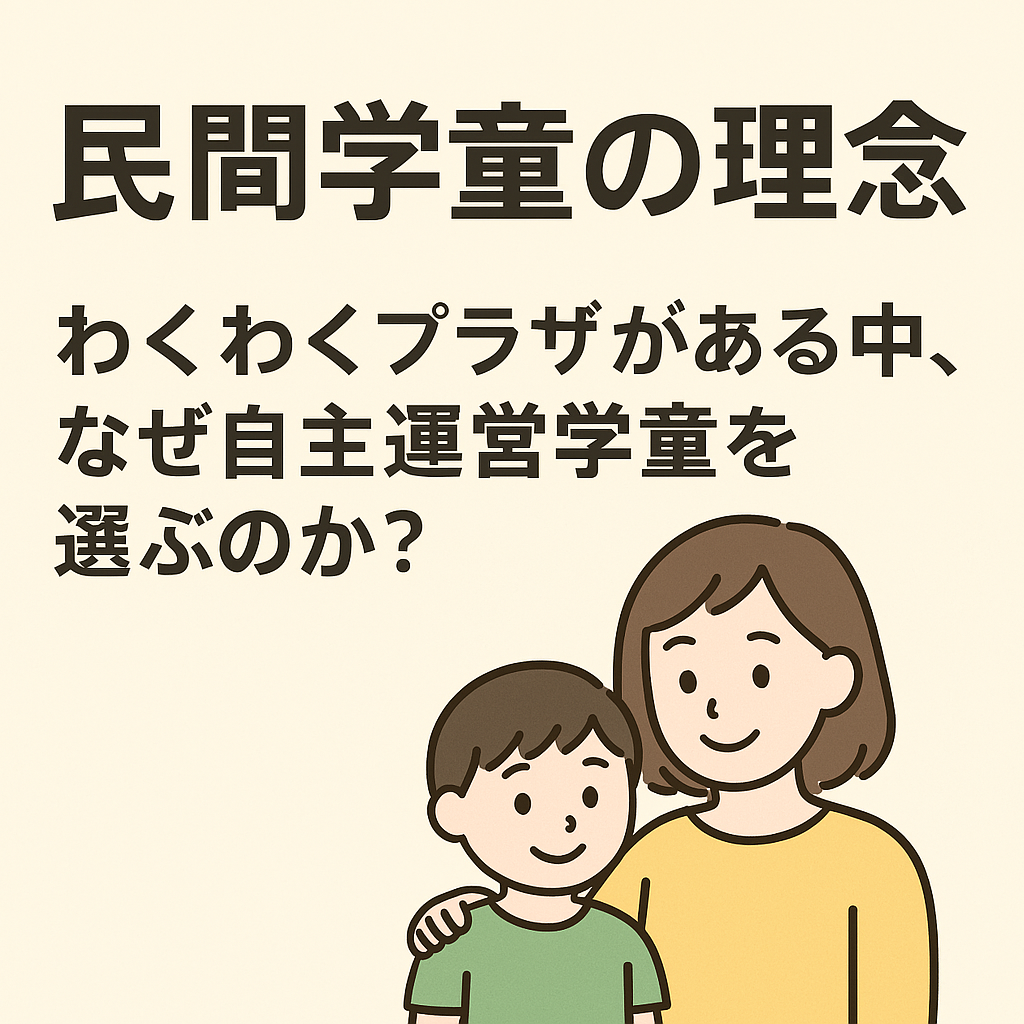

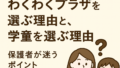
コメント